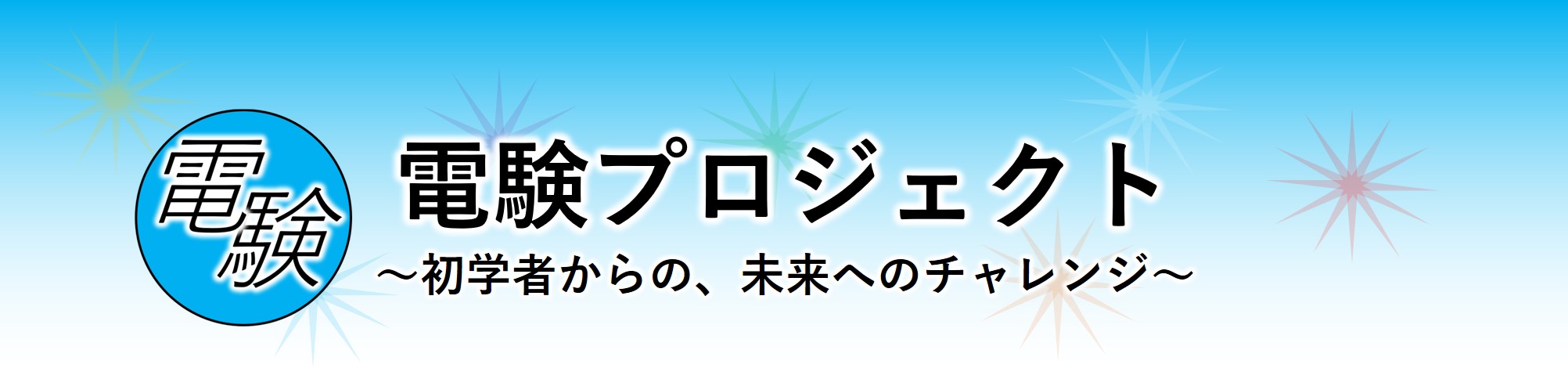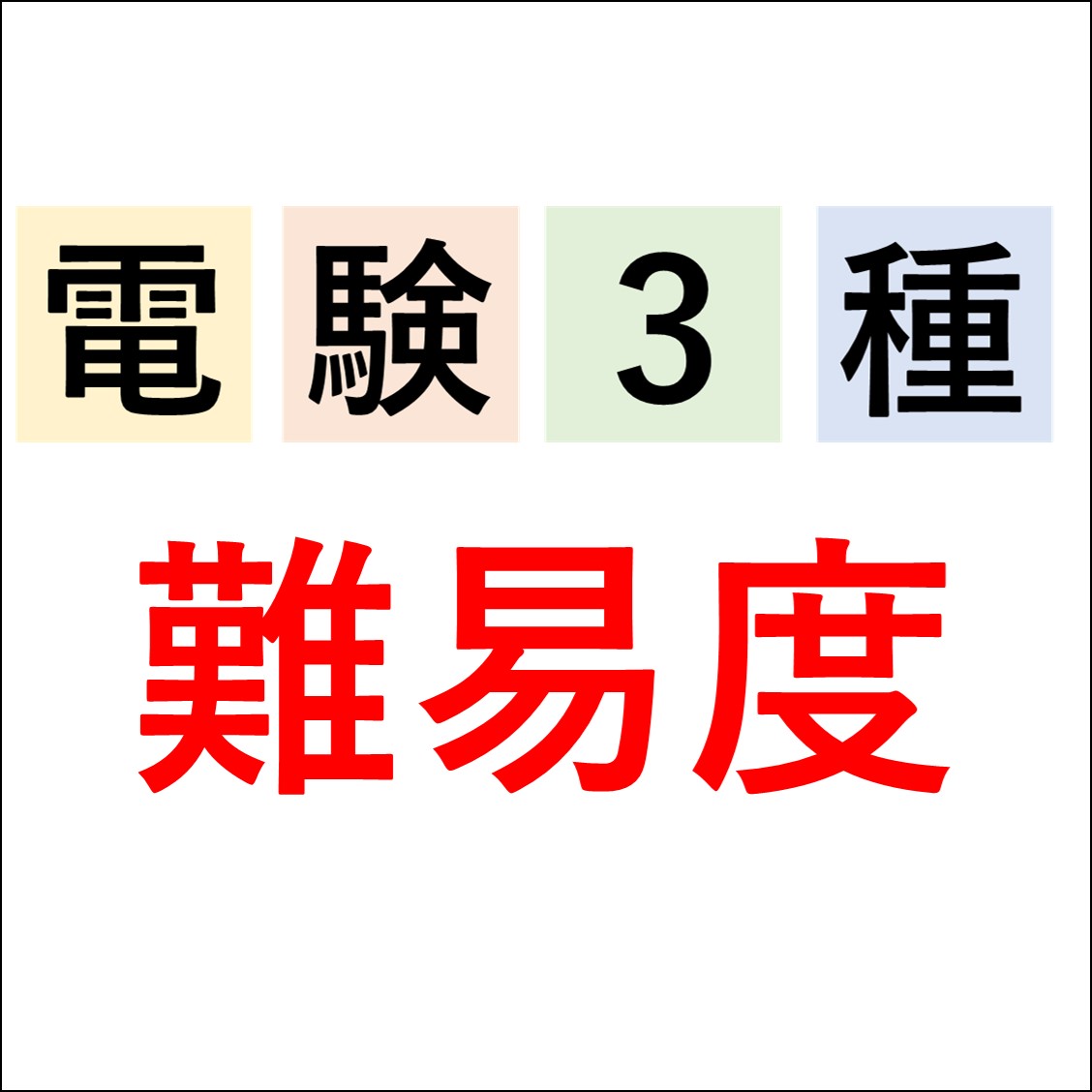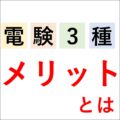電験三種(第三種電気主任技術者試験)は、昔から「理系資格の登竜門」と呼ばれる国家試験です。
ここ数年、合格率の数字だけを見ると「前より簡単になったのでは?」と感じる人も多いでしょう。
では実際のところ、電験三種は本当に誰でも取れる資格に変わったのでしょうか。
本記事では、過去の傾向と現在の状況を整理して解説します。
電験三種の合格率の推移
- 従来の筆記試験時代は 合格率8~9%前後 が一般的で、「狭き門」と言われていました。
- 近年は CBT方式(パソコン受験)の導入により、受験機会が増えたことで 合格率10~20% に上昇。
- 「合格率が上がった=簡単になった」と誤解されがちですが、これは必ずしも問題の難易度低下を意味するものではありません。
出題形式の変化と学習環境の変化
- CBT方式の導入:試験日程を自由に選べるようになり、受験しやすさが向上。
- 参考書・解説サイトの充実:初学者向けの教材やオンライン学習サービスが普及し、効率的な学習が可能に。
- 出題範囲は依然として広い:理論・電力・機械・法規の4科目で、基礎から応用まで幅広く問われる点は変わっていません。
「誰でも取れる資格」ではない理由
- 数学的素養が必要
分数・平方根・三角関数といった基礎計算が苦手な人には大きな壁となります。 - 4科目合格のハードル
一度にすべて合格する必要はありませんが、科目合格制度を活用しても 4科目を数年以内に突破 するのは大きな負担です。 - 実務レベルに直結する知識
電気主任技術者として設備を管理するための知識が求められるため、基礎を暗記だけで突破するのは難しいのが実情です。
4. 近年の「取りやすさ」は何に由来するか?
- 学習機会の増加:通信講座や動画教材が広まり、独学が苦しい人でも学びやすい環境に。
- 受験機会の拡大:年2回の試験日程で「一発勝負の緊張感」が減り、実力を発揮しやすくなった。
- 合格者数の調整:電気主任技術者の人材需要に応じて、合格者数が全体的に増やされている可能性も。
まとめ:難易度は下がったが「誰でも取れる」わけではない
結論として、電験三種は昔に比べて受験環境が改善し、合格しやすくなったことは確かです。
しかし依然として「基礎数学力」「電気工学の理解」「4科目合格の持久力」が問われる試験であり、無対策では絶対に合格できない資格です。
電験3種を取得すれば、
- 電気主任技術者として選任可能 ― 独占業務に就ける。
- キャリアアップ・転職に有利 ― 電気関連企業では資格手当が支給される場合も多い。
- 将来性の高さ ― 再生可能エネルギーやインフラ需要の拡大により、安定した需要がある。
といったメリットがあります。
「難しいのでは?」と尻込みせず、まずは試験制度や出題傾向を知るところから始めてみましょう。