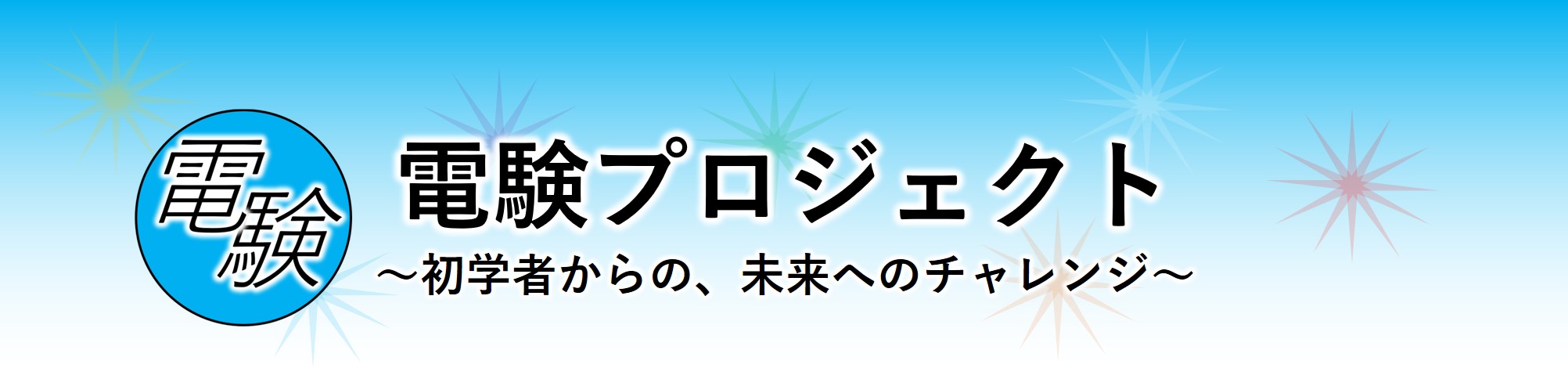電気主任技術者は、工場・ビル・発電所など大規模電気設備の安全運用を担う国家資格者です。
近年「人手不足」「いや、すでに飽和している」といった両極端な声を聞くことも増えてきました。
果たして実際はどうなのでしょうか。本記事では、電気主任技術者の需要や将来性をわかりやすく解説します。
電気主任技術者とは?
電気主任技術者は、一定規模以上の電気設備を持つ事業所に必ず選任が義務付けられています。
設備の保安監督や点検、トラブル対応を担うため、法令で定められた「必置資格」です。
そのため資格そのものが「不要になる」可能性は極めて低いといえます。
2. 現状の人材トレンド
電気技術者試験センターの統計によれば、これまでに第三種で約17万人、第一種・第二種を含めて累計約18万人が合格しています。
しかし有資格者の多くは高齢化しており、現役で従事できる人材は減少傾向にあります。今後はさらに人材不足が深刻化すると予想されます。
(出典:電気技術者試験センター「電気主任技術者試験の概要」)
3. 人手不足は本当?それとも飽和?
「人手不足」と「飽和」の両方の声があるのは、勤務環境やエリアによる差が大きいからです。
- 人手不足の現場:地方の中小規模工場やビル管理。求人は多いが担い手が少ない。
- 飽和しているように見える現場:都市部の大手企業や公務員枠。人気があり倍率が高い。
要するに、全国的には需給ギャップが存在し、職場によって「不足」と「飽和」が同時に起きている状況です。
4. 将来性と今後の需要
- 再生可能エネルギーや電気自動車の普及で電気設備の管理需要は拡大
- 高齢化により今後も現役技術者の退職が続く
- 資格取得者の若年層が不足しており、企業は人材確保に苦労している
以上から、電気主任技術者の需要は今後も高止まりすると予想されます。
資格が「なくなる」ことはなく、むしろ担い手不足が深刻化する分野といえます。
5. まとめ
電気主任技術者は、法律で義務付けられた必置資格であり「なくなる」ことはありません。
ただし、保有者数は多いものの実務経験者が不足しており、業界全体では人材不足が続いています。
まずは電験3種から始めよう
電気主任技術者の入口となるのが第三種電気主任技術者(電験三種)です。
電験三種に合格すれば、事業用電気工作物やビル・工場の電気設備で主任技術者として選任されることができます。
- 国家資格としての信頼性が高い
- キャリアアップ・転職で有利
- 電気分野の基礎知識を幅広く習得できる
電気主任技術者の将来性に関心を持った方は、まず電験三種の学習からスタートするのがおすすめです。
試験制度も改善され、しっかり学習すれば合格のチャンスは十分にあります。
初めての方は、「初学者向け 電験3種 合格マニュアル」も参考にしてください。