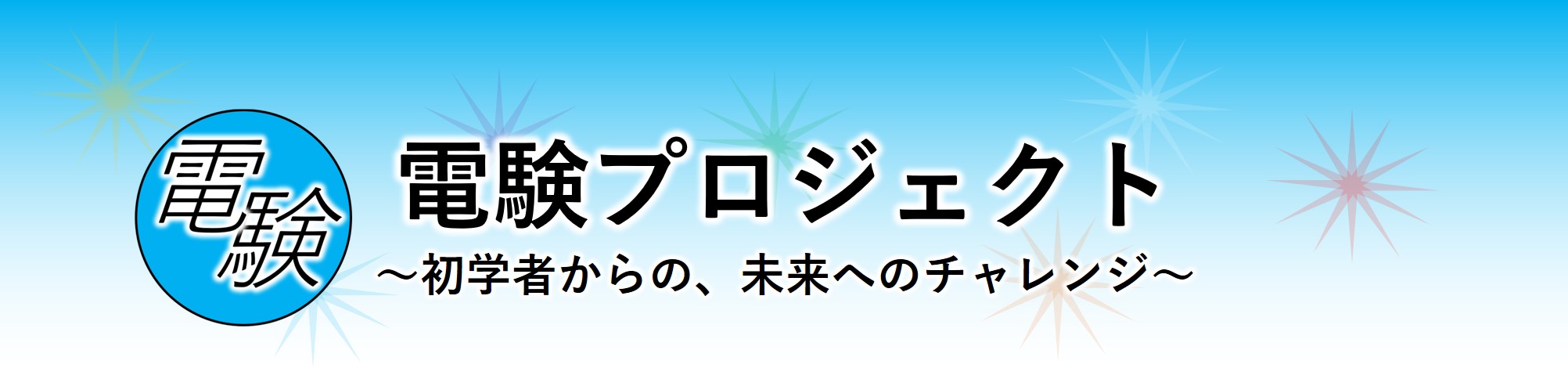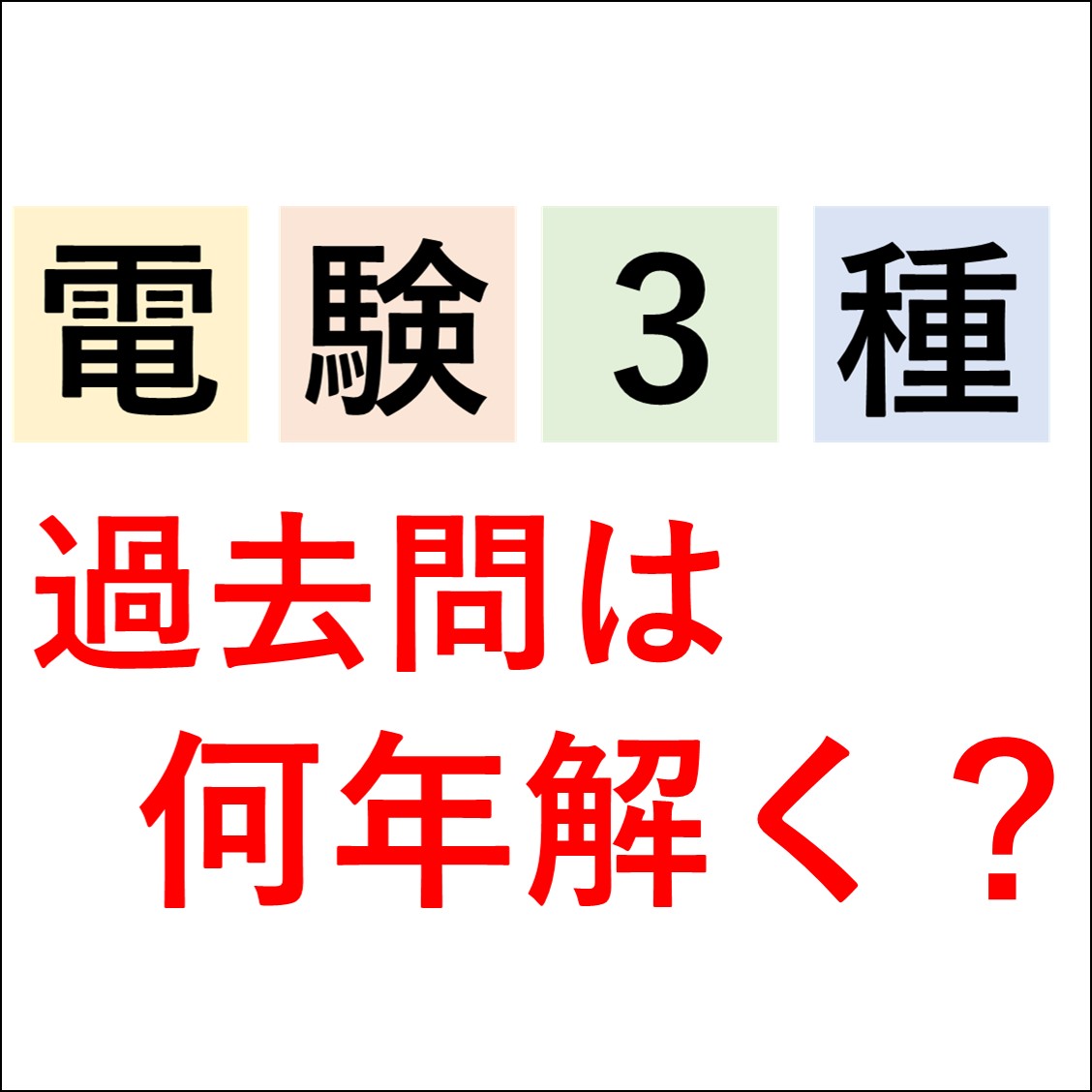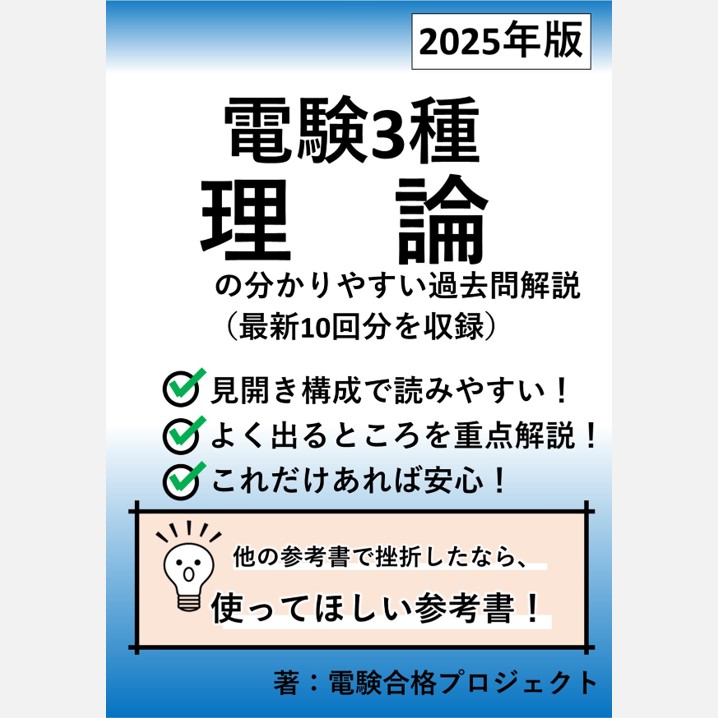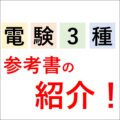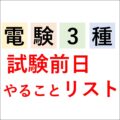「過去問は何年分解けばよいのか」という疑問は、試験対策を始めた初学者が最初に直面する課題の一つです。
結論として、初期段階では最新10回分を徹底的に対策することが、最も効率的かつ効果的です。
本記事では、その理由と効率的な進め方を具体的に解説します。
初学者が直面する3つの悩み
電験3種の対策を始めた初期段階では、次のような悩みが多く見られます。
- 学習範囲をどの程度に設定すればよいのか判断できない
- 最新の問題と過去の問題、どちらを優先すべきか迷う
- 復習に時間がかかり、演習が計画通りに進まない
この段階では、まず範囲を適切に絞り、出題傾向の把握と基礎の理解を優先することが、合格への近道となります。
そのための最適な一歩が、最新10回分からの着手です。
初学者が最新10回分から着手すべき理由
主な理由は3つあります。
直近の出題傾向と頻出テーマを把握できる
最新10回分を演習することで、特に最近頻出の出題テーマを網羅的に把握できます。
また、毎年出題される分野と数年ごとに出題される分野の区別が明確になり、学習の優先度を的確に設定できます。
苦手をリスト化するのに十分な問題量である
過去問を10回分解けば、出題のバラツキもなく、自然に苦手な分野が分かります。
これらを苦手分野のリスト化しておけば、重点的に復習すべき範囲を明確にでき、学習効率が向上します。
現実的な問題量である
いきなり20年や30年分の過去問を解こうとすると、かえって疲れます。
しかし、最新の過去問10回分であれば、問題量的にも現実的です。
1週間や2週間など、現実的な短期の目標を決めて、まずは問題を解き始めましょう。
最新10回分を効率的に進めるためのポイント
頻出テーマの要点を正確に理解する
単に正解することを目的とするのではなく、頻出テーマに関する重要な要点や公式の意味・使い方まで理解します。
過去問を通じて実際の公式の使い方を体得することで、類題や応用問題にも対応しやすくなります。
自力で解いた後に解説を確認する
まずは自分の力で問題を解き、その後で解説を確認します。
途中で行き詰まった場合や解き方が思いつかない場合は、無理をせず解説を見ても構いません。
早い段階で正しい解法や考え方に触れることも、理解を深めるためには有効です。
初学者にもわかりやすい過去問解説を使う
過去問は解説の質によって学習効率が大きく変わります。
専門用語が多すぎたり、数式だけで説明されている解説は、初学者にとって理解の妨げになります。
図解や具体例が豊富で、「なぜそう解くのか」という理由まで丁寧に説明し、かつ試験で狙われやすい要点を絞って網羅している参考書を選びましょう。
さらに、無駄な知識を省き、重要事項だけを厳選して網羅している教材なら、効率よく得点源を固められます。
こうした参考書を使うことで、重要知識を漏らさず身につけられ、理解の定着と学習モチベーションの維持につながります。
10回分を終えた後のステップアップ
最新10回分をやり切った後は、以下の学習が効果的です。
- 誤答や不正解が多かった問題を抽出し、分野別に重点演習する
- 必要に応じて過去の年度まで範囲を拡大し、出題パターンの抜けを補完する
- 模擬試験や予想問題集で初見問題への対応力を養う
まず10回分で基盤を固め、その後に応用範囲へ学習を広げる二段構えが理想的です。
まとめ
電験3種の初期段階で「過去問は何年分解けばよいのか」と迷っている場合は、最新10回分に集中してください。
この範囲を1巡し、苦手分野のリストを作成することが最優先です。
その上で、弱点補強や範囲拡大を行うことで、効率的かつ着実に合格に近づけます。
\文系・初学者に寄り添った、理論!/
著者:電験合格プロジェクト
内容:初学者から分かりやすい電験3種 理論の過去問解説
使いやすい完全見開き構成
最新10回分を収録